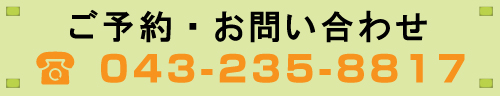こんにちは。四街道スマイル歯科の院長水野です。
今日は、「オーバーブラッシング」についてお話しますね。
皆さんは毎日の歯みがき、どのくらい力を入れてしていますか?
「しっかり磨かないと汚れが落ちない」と思って、ゴシゴシ強く磨いてしまう方は少なくありません。
けれども、実はその“強すぎる歯みがき”が、歯や歯ぐきに思わぬダメージを与えてしまうことがあります。
これを「オーバーブラッシング」と呼びます。
今日はその影響と、正しいケアについてお話しします。
🪥 オーバーブラッシングで起こること
強い力で歯ブラシを動かし続けると、歯ぐきや歯の表面に次のような変化が見られることがあります。
– 歯ぐきが下がる(歯肉退縮)
歯ぐきが少しずつ下がってしまい、歯が長く見えるようになります。
見た目だけでなく、歯の根元が露出してしまうため、しみやすくなる原因にもなります。
– 歯ぐきに傷がつく
ブラシの毛先が強く当たりすぎると、歯ぐきに小さな傷ができてしまいます。
繰り返すことで炎症や出血につながることもあります。
– 歯ぐきが厚く盛り上がる(フェストゥーン)
刺激を受け続けた歯ぐきが、部分的にふくらんでしまうことがあります。
見た目が気になるだけでなく、汚れがたまりやすくなるため、むし歯や歯周病のリスクも高まります。
– 歯の根元が削れてしまう(くさび状欠損)
歯ブラシの摩擦で、歯の根元が少しずつ削れてしまうことがあります。
これも「しみる」原因になり、進行すると治療が必要になります。
🪥 なぜ起こるのか?
原因は「ブラッシングの仕方」と「歯みがき粉の選び方」にあります。
– 力を入れすぎてゴシゴシ磨く
– 硬い毛の歯ブラシを使う
– 研磨剤が強めの歯みがき粉を毎日使う
こうした習慣が積み重なることで、歯や歯ぐきに負担がかかってしまうのです。
🪥 知覚過敏との関係
オーバーブラッシングによって歯ぐきが下がったり、歯の根元が削れたりすると、冷たい水や甘いものが「キーン」としみるようになります。
これが知覚過敏です。
知覚過敏には軽いものから重いものまであり、状態に合わせて治療法が変わります。
– 軽度の場合:専用の薬剤を塗布したり、歯みがき粉を工夫することで改善します。
– 重度の場合:削れてしまった部分を樹脂で補ったり、歯ぐきを再生する治療が必要になることもあります。
つまり、早めに気づいて対処することがとても大切なのです。
🪥 正しいブラッシングと定期的なメンテナンス
歯を守るためには「強く」ではなく「やさしく」が基本です。
– 歯ブラシは鉛筆を持つように軽く持ち、力を入れすぎない
– 毛先を歯と歯ぐきの境目に当て、小刻みに動かす
– 硬すぎない歯ブラシを選ぶ
– 歯みがき粉は研磨剤が少なめのものを選ぶ
そして何より大切なのは、定期的に歯医者さんでチェックを受けることです。自分では気づきにくい小さな変化も、プロの目なら早めに発見できます。
定期的なクリーニングで汚れを落とし、正しい磨き方を確認することで、オーバーブラッシングのリスクを減らすことができます。
🪥 まとめ
「しっかり磨く」ことは大切ですが、「強く磨く」ことは逆効果になる場合があります。
オーバーブラッシングは歯ぐきの下がりや傷、歯の削れ、そして知覚過敏の原因にもなります。
やさしいブラッシングと、定期的な歯科医院でのメンテナンス。これが、歯を長く健康に保つための一番の近道です。
毎日の習慣を少し見直すだけで、未来の歯の健康が大きく変わります。ぜひ今日から「やさしい歯みがき」を心がけてみてくださいね。