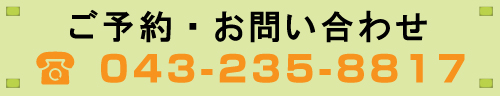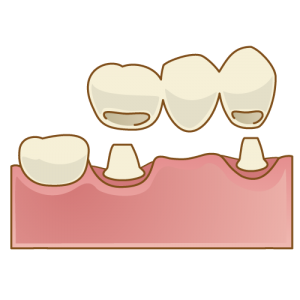こんにちわ、院長の水野です!
今日は、「歯周病の治療」についてお話しますね。
歯周病は、主に歯と歯茎の間の汚れが原因となり、歯の周りの組織に炎症が広がる病気です。
病気が進むと痛みや膿が出たり、骨に炎症が起こると徐々に溶けていくので、そこに支えられている歯がグラグラして抜けてしまいます。
歯周病は、歯肉炎(歯肉が炎症を起こした状態)と歯周炎(歯肉炎を放置して骨が溶けて始めている状態)の2種類に区別されます。
歯周病の治療は、原因となる汚れの除去が基本となります。
歯肉炎の場合は歯の表面の歯垢を除去しますが、歯周炎がひどくなると歯茎ぐき中の歯垢除去などを丁寧に行います。
治療を行うことで炎症が治まり、歯茎が引き締まり、出血が少なくなります。
歯茎を触る処置なので、2~3日は痛みがでることもあります。
また歯周病は、生活習慣病であり高血圧などと同じで完治することはありません。
毎日のセルフケアと定期的な歯医者さんでのメンテナンスで進行・悪化を防いでいく必要があります。
もし歯茎の痛みや出血などありましたら、一度、歯医者さんを予約してみてはいかがでしょうか。