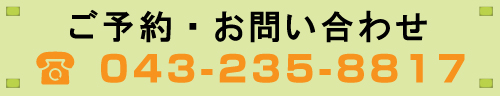こんにちわ、院長の水野です。
本日は、小児歯科医療についてお話ししますね。
小児の歯科医療は、患児や保護者さんの気持ちに寄り添い、見守るという姿勢がだとても大切だと考えています。
近年、患児や保護者さんが対話を通じて語る「病気になった理由や経緯」などの“物語”から、医師が病気の背景や人間関係を理解し、
患児の抱えている問題に対して全人的にアプローチしていこうとする臨床手法が注目されており、
小児歯科医療では臨床手法に基づく医療の実践が重要となってきています。
乳幼児期は一生のうち最も成長スピードが速く、日々変化していること、食べる、噛む、話す、味わうなど生活の基本となる機能を獲得するための大切な時期です。
小児歯科医療は、子どもの特性を理解した上での対応が求められます。