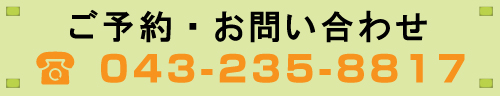みなさん、こんにちは。四街道スマイル歯科の院長水野です。
今日は「口腔カンジダ症」について、少し丁寧にお話ししてみたいと思います。
難しい専門用語はできるだけ使わず、日常の中で理解しやすいようにまとめました。
🌱 カンジダ菌ってどんな菌?
カンジダ菌は、もともと私たちの口の中に普通に存在している菌です。
いわゆる「常在菌」と呼ばれるもので、健康な状態では悪さをせず静かに暮らしています。
ところが、体の抵抗力が落ちてしまうと、この菌が増えてしまい「口腔カンジダ症」という病気を引き起こすことがあります。
🌱 症状はどんなもの?
口腔カンジダ症は、強い痛みや耐えられないほどの症状が出ることは少なく、気づかないまま過ごしてしまう方もいます。
代表的な症状には以下のようなものがあります。
– 舌や頬の粘膜に白い膜のようなものがつく「白いカンジダ症」
– 入れ歯の下の粘膜が赤くただれてしまう「赤いカンジダ症」
白い膜は「白苔(はくたい)」と呼ばれることもありますが、無理にこすり取ると粘膜を傷つけてしまうので注意が必要です。
🌱 口腔以外にも起こるカンジダ症
カンジダ菌は口の中だけでなく、皮膚や膣などにも症状を起こすことがあります。
つまり、全身の抵抗力が下がると、いろいろな場所でトラブルを起こす可能性があるのです。
🌱 入れ歯とカンジダ菌の関係
特に入れ歯を使っている方は注意が必要です。
入れ歯の清掃が不十分だと、カンジダ菌をはじめ多くの細菌が繁殖してしまいます。
入れ歯の内側に汚れが残ると、その下の粘膜が赤くただれてしまうことがあります。
これが「赤い口腔カンジダ症」です。
入れ歯は毎日きちんと清掃することが大切です。
入れ歯専用のブラシや洗浄剤を使い、細かい部分まで丁寧に洗いましょう。
🌱 予防のためにできること
口腔カンジダ症を防ぐためには、日常のちょっとした習慣が大切です。
– 口の中を乾燥させないこと
水分をしっかりとる、唾液を出すためのマッサージをする、マウスリンスを使うなどが効果的です。
– 毎日のブラッシング
歯や歯ぐきを優しく、時間をかけて磨きましょう。痛みがある部分は特に注意して、強くこすらないようにしてください。
– 入れ歯の清掃管理
入れ歯を使っている方は、毎日の清掃を欠かさないことが重要です。寝る前には外して洗い、清潔な状態で保管しましょう。
🌱 まとめ
口腔カンジダ症は、誰にでも起こりうる身近な病気です。
強い症状が出にくいため、気づかないまま過ごしてしまうこともありますが、放っておくと口の中の不快感や痛みにつながり、食事や会話にも影響してしまいます。
毎日のブラッシング、入れ歯の清掃、そして口の中の保湿を心がけることで予防することができます。
もし「赤くただれている」「白い膜が取れない」といった症状が見られたら、早めに歯科医院に相談してください。
みなさんの毎日の生活が快適で、笑顔で過ごせるように。口の健康を守ることは、全身の健康にもつながります。
ぜひ今日から、口腔ケアを少し意識してみてくださいね。