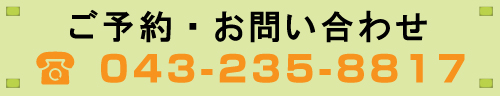こんにちは、院長の水野です。
今日は、歯医者さんで歯石除去を行う際に使用する「スケーラー」という器具についてお話しますね。
歯医者さんで歯石除去を行うと、歯と歯のすき間をフックのような器具でカリカリとしたり、電動のシューっと音のなる器具で歯石を取ってくれたりしますよね。
その時に使われている医療器具が「スケーラー」です。
「スケーラー」は大きく2種類に分類され、「ハンドスケーラー」と「超音波スケーラー」に分かれます。
ほとんどの場合、この2種類を使い分けながら歯石をきれいに除去してゆきます。
ただし、ペースメーカーを使用されている方の場合は、「超音波スケーラー」ではなく「エアースケーラー」を使います。
患者さんの体の状態で、治療方法や診療器具が変わってくるため、問診票の記入やカウンセリングなどのコミュニケーションはとても大切ですね。