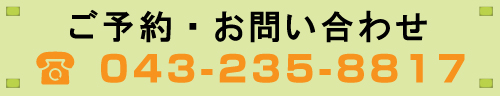こんにちは、院長の水野です。
今日は、「歯のクリーニング」について、お話しますね。
歯医者さんで行う「歯のクリーニング」は、通常のブラッシングではなかなか取り除けない「バイオフィルム」と呼ばれる細菌が作った膜を除去することができます。
また、歯ブラシの届きずらい汚れがたまりやすくなっている所もきれいに落とすことができます。
プラークを除去し、しつこいバイオフィルムも除去するので、歯本来の白さを取り戻すだけでなく、むし歯・歯周病の予防にも効果があります。
毎日のブラッシングと定期的な歯のクリーニングで、より健康な歯を維持することができます。
当院の定期健診では、歯に問題がなければ予防処置として歯のクリーニングを行っています。
また歯のトラブルで来院された方には、全ての治療が終了したらメンテナンスとして歯のクリーニングを行っています。
歯のクリーニングを定期的に行うことで、むし歯や歯周病予防につながります。
しばらく歯のクリーニングをしていないと思ったら、一度、かかりつけの歯医者さんに行ってみてはいかがでしょうか。