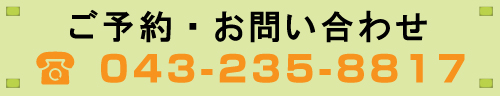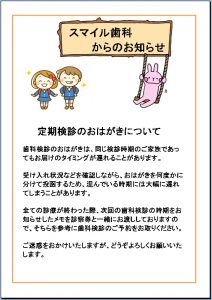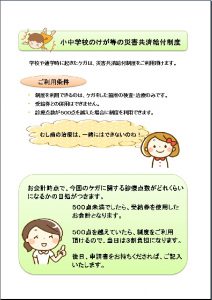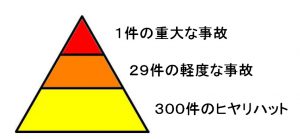こんにちは、院長の水野です。
今日は、小さなお子さんの歯みがきについてお話しますね。
お子さんの歯は、生後7、8ヶ月ごろになると生えだします。
その時期が近づくと歯肉が丸く膨らんでくるので、口の中をのぞいてみてください。
生える順序は、まず下の前歯が2本生え、そして上の前歯、2才以降に乳歯がすべて生えそろいます。
しかし、歯の生える時期などは個人差があるため、少し遅いと感じても特別心配しなくても大丈夫です。
ただ1才3ヶ月を過ぎても生えてこないようなら、一度、歯医者さんに相談してくださいね。
歯が生えだしたらいよいよ歯みがきスタートです。
子どもの歯はむし歯になると進行が早いので、歯の汚れはていねいに落としましょう。
お子さんの歯みがきは、月齢が小さいうちは大人がみがいてあげましょう。
1本、2本のうちは濡らしたガーゼで歯をふく程度でもOKです。
2~3才ごろになるとそろそろ一人みがきができるようになりますが、必ず大人が仕上げ磨きをしましょう。