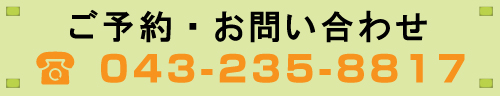こんにちは、院長の水野です。
今日は、「歯周病と感染リスク」について、お話をしたいと思います。
ウィルスが口から粘膜へ侵入する際、口の中の細菌が侵入を手助けしてしまっていることがあります。
数ある細菌の中でも歯周病菌は特に強力で、歯周病菌の助けを借りて侵入したウィルスは増殖して様々な症状を引き起こします。
逆にいえば、ウィルス性の風邪やインフルエンザなどは、歯周病菌を減らすことで感染リスクを低下させることができます。
歯周病は、プラーク(歯垢)という最近の塊の中に潜んでいて、毎日しっかり歯磨きをしても完璧に除去することは難しく、口の中に蓄積されていきます。
日頃の歯磨きに加え、フロスや歯間ブラシなどを使うと除去率がUPします。
また、定期的に歯医者さんで歯のクリーニングを行い、セルフケアでは取り切れなかったプラークを除去すると良いでしょう。
特に、今年は全国でインフルエンザが異例の流行状況となっており、手洗いとうがいに加え口腔環境のケアも心がけてウィルス感染を予防したいですね。